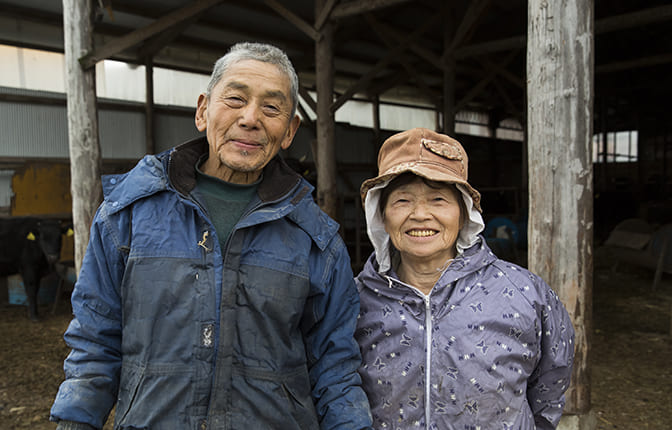高校の時から家を出ていた三女の律子さんが帰ってきたのは2012(平成24)年。きっかけは、東日本大震災と福島第一原発事故。「私もいつ死ぬか分からない」と考えた時、若い時に肉屋をやるといって修業に出たものの、実現せずじまいだったのが心残りだった。
アルバイトで生計を立て、2013年に見浦牧場の牛肉を販売するミートセンターをオープン。これまで牧場経営や肉の販売にはノータッチだったが、肉屋での修業、勤めていた新聞店が発行していた新聞の取材、原稿作成、印刷、イベント企画、経理の仕事の経験や、さまざまなアルバイトでつながった人脈などが、とても役立っているという。「無駄はない。人生はそういうものかもしれないですね」。
修業経験があるとはいえ25年も前の話。肉に関する知識は本やインターネットで必死に勉強し直した。「肉の知識はまだまだ。今はただ一生懸命、皆さんが望まれるものを提供しているだけ」謙虚に言いつつも、楽しそうに次々とお肉のうんちくを語ってくれるから、牛肉の魅力をもっと知りたい、楽しみたいと思えてくる。実際、ここの商品は「こんな詰め合わせなら手軽に楽しんでもらえるかな」という律子さんの工夫がいろいろ。
お父さんについて聞いてみると「スーパーマンだと思う(笑)。あれだけずっと一つのことをやり続けるのは、なかなかできることじゃない。私が子どもの時なんて本当に貧乏で、食べるものもないくらい追い込まれたこともあるけど、投げ出さなかった。父は仕事が生きがいなので、休みんさいとは言わないようにしています。あと何年できるかは神様のみが知っていること。うちの家族は、それぞれがそれぞれの思いで生きていて、牛だけが接点なんです」。牛という一つの夢に家族みんなの心が注がれる。それがこんなにも見浦牧場の絆を強く結んでいる。
次男の和弥さんは高校卒業と同時に見浦牧場に入った。幼いころからトラクターに乗り、牛に囲まれて育った和弥さんにとって、毎日牧場で暮らすのはごく自然なことだった。「悩むことはありませんでした。これといってやりたいこともなかったし、かといって、この牧場を残す! というような使命感があったわけでもないのですが、やってみようと」。
和弥さんいわく理論派のお父さんに対して、自分はほとんど「勘」だという。多分に感性的な側面があり、まず自分の感じるものに従ってみる、そして結果に基づいて理論を構築するというタイプだ。「悪くいえばつじつま合わせ」と笑うが、最初に働く勘も、知らず知らず経験に基づいた説得力を秘めているのではないか。状況に合わせて対処できるのも、引き出しが多いからこそ柔軟に結果を出せるというものだろう。
牛に対する思いを聞くと「牛は特別な存在ではありません。彼らは生きるために全力を尽くす生き物。私には生き物に対する差がないんです。人間もほかの動物も。人間が特別なんていう気もさらさらなく、むしろ人間の方が問題が多い」。
「子どもたちは今は作文で『後を継ぐ』と書いていますが、よく言うわと(笑)。農業が昔みたいに生産特化で生きられる時代ではありません。お上の言うとおりにしていればいいではなく、よほど自分の意志が強くない限り続かないでしょう。今からの農業は『なぜ作るのか』という問いに対して答えを持っていなければ。それでも、子どもが本気でやるなら、もちろん応援します」。
「今後も、今の味は守りたいと思います。もっとおいしくなれば理想ですが、そのためには、このおいしさが何から生まれるのか、血統、飼料、草、水、運動量など、今以上に検証し、理論を確立する必要があると考えています」。
和弥さんの妻の亮子さんは高校時代に和弥さんと出会い、1995(平成7)年に嫁いできた。それまで動物看護師として働いていた動物好き。「牛をペット扱いするクセがいまだにとれない。それが一番ダメなところ。可愛いだけじゃいけないんだけど、どうしようもなく可愛い(笑)」。人が手をかけすぎると、群れに戻った時に餌がとれなかったり、ルールになじめなかったりして、群れから落後し、寿命を縮めてしまうこともあるという。
牛との信頼関係も人と同じ。「近づいても逃げないのは気を許してくれている証拠。牛は自分のお母さんが信頼している人は自分も信頼していいと思うから、代々、信頼の積み重ねです」。取材スタッフが近づくと牛は警戒するが、「気にしなくていいよ」と亮子さんがなだめながら近づくと、落ち着いて見える。
以前、それまで入ってきたことのない下痢が流行し、ひと冬で6頭の牛が死んでしまった。亮子さんは自分を責めひどく落ち込んで、見かねたお父さんに「実家に帰るか」と気遣われるほどだった。しかし「何が原因で死なせてしまったのか、どうしたら治ったのかを検証し、自分の経験にしておかないとまた同じことを繰り返してしまう」そう思い直した亮子さんは「実家に逃げ帰るわけにはいきません」と踏ん張った。「その時、お父さんに認めてもらえたみたいです」。
「お父さんもお母さんも、本当に我慢強い。私をここまで育ててくれて。教わったことをひと言でいうなら家訓の『自然は教師、動物は友、私達は考え斈ぶことで人間である』に込められています。育ててもらったから、教わりたいという人がいれば、自分も何か伝えることができたら」。そんな人にはまずこの牧場を見てほしいという亮子さん。見浦家の人々が積み上げてきたものは、すべて牧場にあるから…。
最後に、哲彌さんの妻の晴江さんから哲彌さんに捧げる「結婚50年目のラブレター」をお届けする(2002年 見浦晴江手記より)。
高校卒業後どうするか? たいした目的意識もなく、ただ漫然と過ごしていた私にとって大きな問題だった。採用試験の申込用紙だけはもらってみたものの、勉強もろくにしていない私には受けてみる勇気もなく、結局何もしないまま卒業してしまった。
私の生まれた集落は、広島県の北海道と言われ、冬は2メートルを超える雪に覆われてしまう、20軒ばかりの小さい集落だが、当時はそれぞれの家に後継ぎの若者がいて、青年団で結構、積極的な活動をしていた。その青年団の仲間に入れてもらって、地域の新聞の紙面作り、原紙切り、ガリ板刷り、今考えると充実した面白い時期だったと思う。
昭和28年3月、青年団の仲間だった主人(哲彌さん)と結婚した。20才そこそこの私たちに、義父は「結婚を期に独立してやってゆけ」と、田圃九反、それに雨漏りがする大きな茅葺き屋根の家を任されたのだ。
その日から、悪戦苦闘が始まった。春とともにはじまる農作業、稲の植え付けの準備である。牛の手綱を取って代掻きもした。大きな二反もある、爪先立ちして歩かないと股まで浸ってしまいそうな深い田圃に入って、2日も3日も田植えをした。
昭和29年1月、長女が生まれた。寒い雪の降った日だった。主人と弟が10キロ離れた八幡まで産婆さんを呼びに行ってくれたが、10時間以上もかかってやっと帰ってきた。産婆さんも、もうかなり年だったと思うが、本当に良く来て下さったものだ。いま思っても感謝感激である。彼の母も、私の母も、早死して居なかったので、子育ては大変だった。風呂が離れにあったので、風呂に入れるのも一大事だった。私が子供と一緒に風呂に入り、あがるときに大声で彼を呼ぶ。彼は大雪の中、すぐに脱げるようにと下駄をつっかけてやってくる。子供を受け取ると、子供が凍ってしまわないうちにと、必死で母屋に駆け込むのだ。あの当時は男親が子育てを手伝うと言う時代ではなかったが、彼はお襁褓の取り替えなど積極的にやってくれた。
昭和29年春、 ボロボロの茅葺き屋根の家を何とかしなければと、思い切って建て替える事になった。向こう見ずな彼は、何も知らないのに山師をやって金を稼ぎ、製材も自分でして費用を節約し、12月に新しい家に何とか入れた。学校みたいな変な家だと悪口を言われたが、少なくとも雪が舞い込む事は無くなった。そして、また春が来た。
当時、牛を使って田起こしをすると、1反に2日かかった。牛を使っていては能率は上げられないと、なけなしのお金をはたいてトラクターを買った。しかし膝の上まで浸かる軟らかい田圃では、役に立たなかった。そこで考えた。湿田だから駄目なのだから、暗渠( あんきょ=地下水路)排水をしよう、と。雪に埋もれてしまう冬には出来ないので、稲作りを休んで、スコップとつるはしだけで、背丈ほどの排水溝を掘って、土管を入れて、又土をもどす。気の遠くなるような仕事だった。しかし、苦労の甲斐あって、暗渠排水をした田圃にはトラクターが入れるようになった。乾田になった田圃は、あの深かった土はどこへ行ったのかと思うほど浅くなって作業が楽になり、能率が上がるようになった。
昭和35年に次女が、36年には長男がまれて、育児が忙しくなった。この頃から病院でお産をするようになった。年子だったので大変だった。長女の時は乳母車が買えなかったので、木の箱の中に布団を敷き、子供をいれて田圃の畦道に連れて行って仕事をしたけれど、次女の時は乳母車が買えた。その中に二人を入れて仕事場を連れまわったものだ。
昭和38年に三女、44年に次男が生また。5人の子供たちを育て、大学まで出すのは容易ではなかったが、奨学金に助けられて、なんとか皆育てる事ができた。学校に行きたくても貧乏であきらめ、独学で電検の二種と三種の資格を取った主人は、子供たちに「学校に行きたければ一度だけチャンスをあげる。家の経済状態では国公立以外は不可能だけど、君達がそれを乗り越えたら全力を挙げて手伝う」と申し渡した。ワンチャンス・ワントライ方式と名付けた壁を、子供たちは皆乗り越えてそれぞれ仕事に付いている。ただ跡を継がせた次男には借りを作ってしまった。
話は前後するが、昭和38年2頭のボロ牛を買い込んで牛飼いを始めた。冬季の交通が困難なので、運搬が必要な出荷や仕入れが少なくて済む、黒牛の繁殖から肥育までの一貫経営をめざしたのだ。京都大学の先生や広島大学の先生が出来ないと太鼓判を押したのに、である。手本がないのだから毎日毎日が戦争だった。しかし一年一年少しずつ牛を増やして、40年でやっと180頭と30町の牧場を( うち10町は小作)作り上げた。40あれば何千頭にも増やすことに成功した人もいるが、家族経営にこだわった私たちにはこれが限界だった。
気が付けば、70才。 がむしゃらに働いてきたが、もう人生の終わり、長いようで、短いようで。
生き物を飼うという事は、一日たりとも休みがない。酪農はヘルパー制度なるものがあるようだが、肉用牛にはそんな話は聞いた事がない。泊まり掛けの旅行など、夢のまた夢。しかし、それが出来なかったからといって、暗い人生だった訳でもない。なにしろ、文明なるもののおかげで、いながらにして世界のニュースを知る事のできる世の中だから、気の持ちようである。
振り返れば、色々あったが、何事も前向きに考えて突っ走る彼のおかげで、ハラハラドキドキ。面白い人生を本当に「ありがとう」。
見浦牧場ミートセンターオンラインショップ
https://miurafarm.shopselect.net/

見浦牧場ミートセンター
〒731-3801 広島県山県郡安芸太田町小板1108
TEL.0826-29-0045
掲載記事内容は取材当時のものであり、
現在の内容を保証するものではありません。